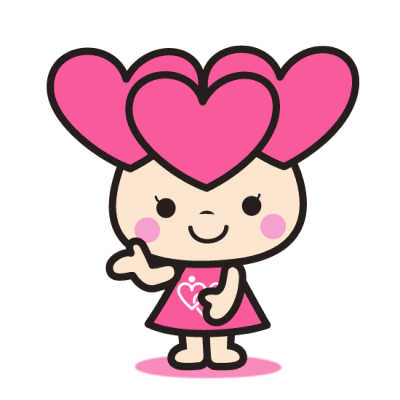~機能訓練通信とやらをはじめてみる~ 第4項:機能訓練指導員としての評価の仕方について②
雪も思ったよりは降らず晴れ間が見えることも増えましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?
デイサービスセンター城北町です\(^^)
前回より少し日にちが空きましたが,前回に引き続き機能訓練を実施するために必要な「評価」の部分でのお話をさせていただきたいと思います.
以前「目標設定」の部分をお話ししましたが,目標を設定するうえでも「評価」というものはとても重要になります.
デイサービスにおける評価方法は大きく分けると3つになります.(もちろん細かくすればいくらでもありますが・・・)
その3つとは・・・
Ⅰ:身体面の機能評価
Ⅱ:認知機能面の機能評価
(Ⅰ・Ⅱ)を合わせてADL(日常生活動作)の機能評価
Ⅲ:家屋状況や家庭環境
の3つになるかと思います.
今回はⅡ:認知機能面の機能評価についてお話していきたいと思います.
認知機能面については,身体機能面のように決まった評価項目はあまりない印象ありますが,大まかにとらえると
①記憶障害(見当識や短期・長期,意味記憶など)
②ADLにおける遂行機能障害(更衣や排泄,歩行など)
③高次脳機能障害(失行や失認など)
の3つが評価できる項目になるかと思います.
また,前情報として利用者の方の疾患名(アルツハイマー型やレビー小体型など)の情報を得ることでどの部分が障害されやすいのか,どのような経過をたどることが多いのかなどの予後予測をすることが可能となります.
評価用紙としては,有名所でいえば長谷川式スケール(HOS-R)やMMSEといった評価方法が存在しています.認知機能障害を得点にてあらわしたものですがあくまでも参考程度にし,実際のADL等の部分での評価がとても重要となっています.
PDF形式になっていますが,実際に当事業所で使用しているMMSE評価用紙になっています.
認知機能障害への評価方法としては上記のようなものがあるかと思います.しかし,認知機能障害において1番の評価ポイントとしては,実際に介助,介護をしている家族のかたなどの大変な部分,困っている部分をしっかりと聴取・情報収集を行っていくことが重要となると思います.記憶やADLが障害されていても,その介助者が大変でなければその部分は優先順位としては低くなるのではないかと考えられます.
そのため認知機能障害のかたへの評価としては,利用者様本人への評価とその周りのかたに対する情報収集や聴取がかなり重要となってきます.また,その部分がしっかりと収集できていると,評価項目やデイサービス等での支援方法も次いで決定してくるものだと考えられます.
今回は,認知機能障害に対する評価方法を記載いたしました.認知機能障害に対しては機能訓練指導員等による紙面的な評価よりも実際に介助にあたっている家族や職員(介護士)等からの情報が必要となることが多いため,多職種連携が求められる形となることが多いと思います.そのため日頃からのコミュニケーションであったり情報交換を行っていけるととても良いのではないかと思います.
次回の更新では,Ⅲ:家屋状況や家庭環境についての記載を行いたいと思います.
よろしくお願いいたします\(^^)/